○荒川浩1) 2)、山口景子1)、監物千代子1)、菊地沙織3)
日下田那美4)、塚越徳子3)、二渡玉江3)
1)桐生厚生総合病院
2)元群馬大学大学院保健学研究科博士前期課程
3)群馬大学大学院保健学研究科
4)元群馬大学大学院保健学研究科
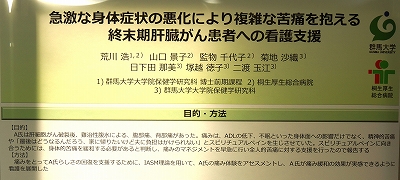
【はじめに】
A氏は肝細胞がん破裂後、難治性腹水による、腹部痛、背部痛があった。痛みは、ADLの低下、不眠といった身体面への影響だけでなく、精神的苦痛や「最後はどうなるんだろう、家に帰りたいけど夫に負担はかけられない」とスピリチュアルペインを生じさせていた。スピリチュアルペインに向き合うためには、身体的苦痛を緩和する必要があると判断し、痛みのマネジメントを早急に行い全人的苦痛に対する支援を行ったので報告する。
【研究方法】
痛みをとってA氏らしさの回復を支援するために、IASM理論を用いて、A氏の痛み体験をアセスメントし、A氏が痛み緩和の効果が実感できるように看護を展開した。尚、文書で事例発表の同意を得た。
【結果】
A氏は、「痛みを何とかして取りたい」、「痛みを取って、自分のことは自分でできるようになりたい」という気持ちが強かった。しかし、レスキュー導入後に嘔吐があり、効果的にレスキューを使用することができず、痛みを我慢して過ごしていた。A氏の苦痛を緩和するために、A氏の痛みの体験をスタッフ全体で共有し、レスキューの正しい知識を提供し、副作用、効果をA氏のそばで一緒に確認した。その結果、レスキューに対する抵抗感が薄れ、主体的に疼痛コントロールを図り、効果を実感することができるようになった。疼痛コントロールが可能になったことで、何とか家に帰っても過ごせるという気持ちになり、2泊3日の外泊を実現することができた。
【考察】
A氏の「自分のことは自分でできるようになりたい」という思いを実現し、主体的に疼痛コントロールを行えるようになったことは、A氏の自己の尊重につながったと考えられる。A氏は、看護師がいつでもそばにいて話を聞いてくれる存在であること知り、決して自分は孤独ではなく、他者に存在を認められ周囲に支えられ生きていることが実感できたと考えられる。
プログラムへ戻る